「長靴をはいた猫」はなぜ長靴をはく必要があったのか?あらすじや教訓も考察
さまざな絵本やアニメーションで展開されている「長靴をはいた猫」。とても有名な童話で、猫が主人の人生を切り拓いていくさまは見事ですが、そもそも何で猫は長靴をはいているのでしょうか。そこには、作品が書かれた時代背景と深い繋がりがありました。この記事ではあらすじや教訓とともに、猫が長靴をはく理由を解説していきます。あわせておすすめの絵本も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
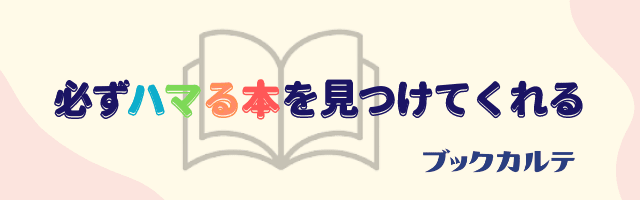
「長靴をはいた猫」のあらすじ
ヨーロッパに伝わる民話「長靴をはいた猫」。世界各地に類話があります。ここではもっとも有名とされている、フランスの詩人シャルル・ペローが執筆した童話集におさめられているもののあらすじを紹介しましょう。
あるところに粉挽き職人と3人の息子がいました。粉挽き職人が亡くなり、息子たちに遺産が分配されます。長男には粉挽き小屋を、次男にはロバを、そして三男には1匹の猫が割り当てられました。
三男が「こんなもの腹の足しにもならない」と嘆いていると、なんと猫が話しかけてきます。「大丈夫ですよ、ご主人様。私が必ずあなたを立派にしてさしあげます!」
そして猫は、長靴と袋を求めました。三男が言うとおりにしてやると、猫は長靴をはき、袋を持って出かけていきました。
まず猫はウサギを捕まえ袋に詰めると、王様のもとへ持っていきます。「これは我が主、カラバ侯爵から王様への贈り物です」と言いました。「カラバ侯爵」というのは猫の飼い主である三男のことで、これは真っ赤な嘘なのですが、それ以降猫がたびたび献上物を持ってくるため、王様は「カラバ侯爵」に好印象を抱くようになりました。
そんなある日、猫は三男に対し、川で水浴びをするよう伝えます。三男が言われたとおりにしていると、そこに王様と、娘の王女がやってきました。すると猫は、「カラバ侯爵が水浴びをしている最中、大切な服を盗まれてしまった」と言います。
王様は、水浴びをしている男こそがいつも貢物を持ってきてくれる「カラバ侯爵」であると知ると、三男に衣服を与えました。それから「カラバ侯爵」の邸宅へ王様たちを連れて行くこととなり、猫が馬車を先導します。
その道すがら、猫は百姓に出会うたびに「ここはカラバ侯爵の土地であると言え、さもなくば八つ裂きにしてしまうぞ」と言ってまわりました。
本当は「オーガ」という怪物が治めている土地でしたが、八つ裂きにされたくない百姓は従うしかありません。猫の後ろに続く王様に「ここは誰の土地か」と問われると、「カラバ侯爵の土地でございます」と応じ、王様は広い領地を持つカラバ侯爵に感心するばかりなのでした。
そして一行が到着したのは、オーガの邸宅です。猫はオーガをおだててライオンや象に化けさせると、「いくらあなたでも、小さなネズミにはなれないでしょう?」と挑発をします。誘いに乗ったオーガがネズミになると、猫は捕まえて食べてしまいました。
こうしてオーガの城を奪った猫は、邸宅を「カラバ侯爵の城」として王様と王女様を迎え入れるのです。
三男はもともと育ちがよく、優しい性格をしていたため、王女はしだいに彼に心惹かれるようになりました。王様の提言もあり、やがて2人は結婚し、幸せになったといいます。そして猫もまた、貴族へと取り立てられました。
「長靴をはいた猫」はなぜ「長靴」をはく必要があったのか
あらためてあらすじを振り返ってみると、なんとも不思議なお話です。猫が主人である三男を出世させていくのも興味深いですが、そもそもなぜ猫は「長靴」を求めたのでしょうか。タイトルになっているにもかかわらず、物語のなかで重要な役割を果たしているようには見えません。
ここで当時の時代背景を考えてみましょう。
シャルル・ペローが「長靴をはいた猫」を出版したのは、1697年です。革命が起こる前のフランスが舞台で、貴族が絶大な権力をもっていた時代でした。実は本作における「長靴」は「ブーツ」を指していて、当時においてブーツすなわち貴族の象徴だったのです。
つまり長靴をはいていれば、百姓であろうと子どもであろうと、そして猫であろうと貴族に見えたということ。
長靴をはいた猫は、王様や王女、そして百姓たちにも対等、もしくは上の立場から接しています。王様は猫からの献上物をなんの不思議もなく受け取っていますし、百姓たちも「ここはカラバ侯爵の土地と言え」という猫の命令に従っています。
それは本作における長靴をはいた猫が、貴族と同等とみなされていたからに他なりません。どんな者でも長靴さえはけば貴族になり、そして人々は見せかけの権力に簡単に屈してしまう……猫に長靴をはかせることで、シャルル・ペローの貴族社会に対する皮肉を感じることができるのではないでしょうか。
「長靴をはいた猫」から学べる教訓は?
見かけの印象だけでは、そのものの力量は測れない。
兄たちが譲り受けた粉挽き小屋やロバは、確かに価値のあるものに思えます。仕事に使うこともできるし、お金に換えることもできる、実用的だといえるでしょう。
しかし最終的には三男が受け取った猫が、持ち主をもっともよい方向へと導いてくれました。一見何の役にも立たなそうな猫ですが、見た目だけでは本質を測ることはできないことがわかるでしょう。
また本作は、楠山正雄によって「猫吉親方」というタイトルで翻訳されています。その最後は、次の言葉で締めくくられていました。
「親ゆずりの財産に、ぬくぬくあたたまっているよりも、若いものは、自分の智恵と、うでを、もとでにするにかぎります。」
あるものをそのまま受け継いでいくのではなく、自分の力で人生を切り拓くことが大切なのです。
美しいイラストが魅力的な「長靴をはいた猫」
- 著者
- シャルル・ペロー
- 出版日
日本で展開されるアニメーションや絵本では、人間のように衣服をまとっている姿で描かれることの多い猫ですが、本作に登場するのは毛並みや背中の丸みなどまさに本来の猫そのもの。そんな様子で長靴をはき、人間とわたりあう姿に不思議な魅力がつまっています。
文章のボリュームが多いので小さなお子さんには少々難しいかもしれませんが、美しいイラストは大人が楽しむのにも十分なもの。プレゼントにもおすすめです。
小さなお子様にもおすすめの絵本
- 著者
- シャルル ペロー
- 出版日
- 1980-05-20
スイスの画家、ハンス・フィッシャーが手掛けた作品。繊細でありながら躍動感のあるイラストを堪能することができます。
長靴をはく練習をする様子や、百姓に命令をする際の怖い顔の練習をする様子など、独自の展開も魅力的です。文章もリズムがよくて読みやすく、読み聞かせにもおすすめの一冊です。
「長靴をはいた猫」など童話の新たな一面を知れる一冊
- 著者
- シャルル ペロー
- 出版日
- 1988-12-01
「長靴をはいた猫」をはじめ多くの童話を残しているシャルル・ペロー。有名なグリム童話も彼の話をもとにしているものが多いのですが、実は私たちがよく知っている「赤ずきん」や「シンデレラ」の結末は、本来はもっと残酷で血なまぐさいものでした。毒をはらんだ、童話の新たな一面を知れる一冊です。
澁澤龍彦の訳は、シンプルながらも日本語の美しさが伝わってくるもの。片山健のイラストもセクシャルな雰囲気をもっています。一味違う童話の世界をお楽しみください。