覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰 (Sanctuary books)
2013年05月25日
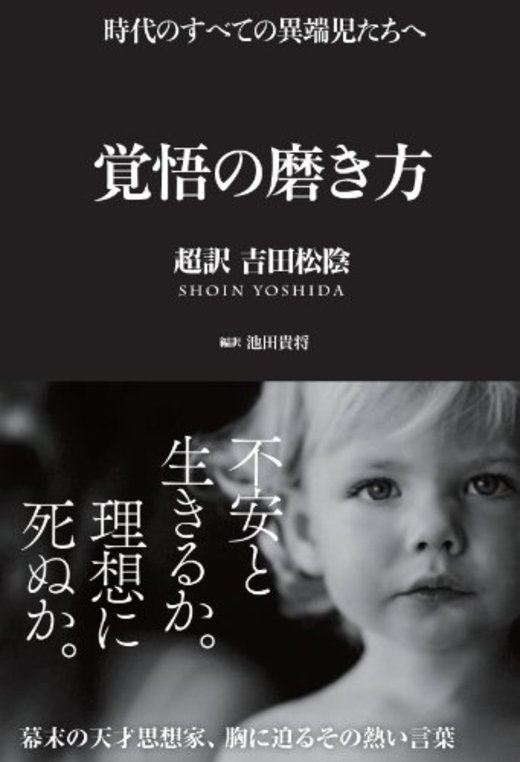
ライブやらでファンの方から差し入れを頂くときがあります。とても感謝しています。そして、この連載を始めてから本を頂くことがとても多くなりました。今日は自分の感性だけじゃ選ばなかっただろう、頂いた3冊をご紹介します。

大ヒット作『すべてがFになる』の森先生の著作です。僕も森先生の小説は何冊か読んだことがあったのですが、エッセイや随筆のようなものも書かれていることは知りませんでした。
- 著者
- 森博嗣
- 出版日
- 2016-09-10
「不安と生きるか、理想に死ぬか」の言葉を残した幕末の思想家、吉田松陰の超訳本です。簡単に言うと“幕末の凄い人の教えを死ぬ程分かりやすくした本”になります。現代を生きる僕たちにも、その言葉はいくつものヒントになり得ます。覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰 (Sanctuary books)
2013年05月25日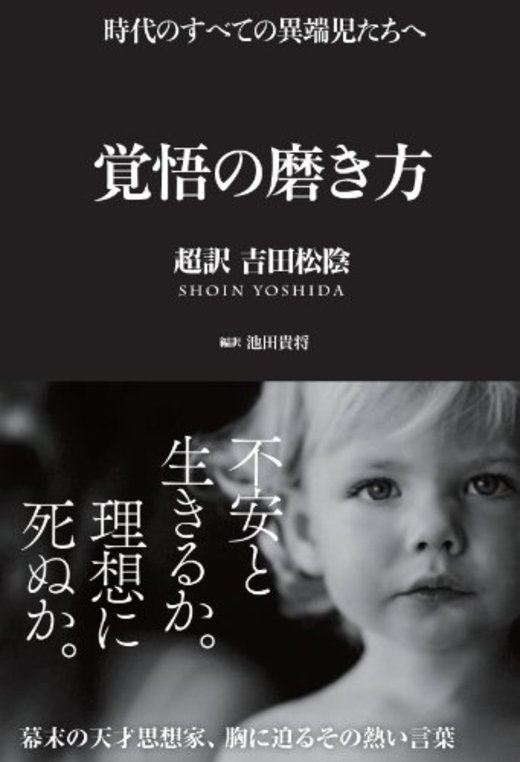
西野さんのことは「キングコングのよく炎上しているひと」という印象しかありませんでした。クラウドファンディングや無料公開など、これまで僕がやってきた活動と近いようなことをされている方だとはおもっていたのですが、「炎上しまくっているひと」という理由から、敬遠してあまり知ろうとしませんでした。
- 著者
- 西野 亮廣
- 出版日
- 2016-08-12
本と音楽
バンドマンやソロ・アーティスト、民族楽器奏者や音楽雑誌編集者など音楽に関連するひとびとが、本好きのコンシェルジュとして、おすすめの本を紹介します。小説に漫画、写真集にビジネス書、自然科学書やスピリチュアル本も。幅広い本と出会えます。インタビューも。