【第2回】ロマンスがはじまらない
更新:2021.11.29
振り返ると、私を「虫に似てる」と言っていたガキ大将、暗くて口が悪い人、私のことを嫌いな人、そして童貞を絵に描いたような人が好きだった。輪の中心にいたり、勉強ができるタイプではなく、いつも「え、その人? 」と聞き返される人に惹かれてしまう。

ガキ大将は言った。「お前は虫に似ている」
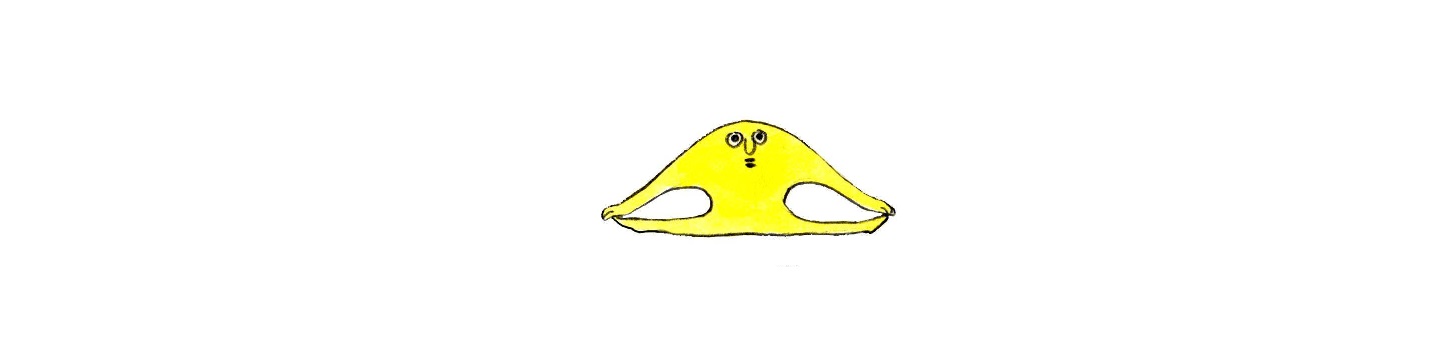
好きな人には意地悪をしてしまうタイプの子供だったので、4年生の時、彼の下駄箱に果たし状をねじ込み決闘を申し込んだ。ラブレターではなく、果たし状である。自分でも思い出しては「なんでだよ」と突っ込むのだけれど、当時はそういう愛情の示し方しか知らなかった。どうにかして、彼とふたりきりの時間を作り出そうとしていたのだ。今であればもう少しスムーズに、LINEで「映画見よう」とでも送ってすませていただろうに。
そして放課後、机と椅子を片付け空っぽになった教室で、私は自分の好きな人と決闘をすることになった。私の得意とする攻撃はもっぱらキック。バレエを3ヶ月習ったという心許ないバックグラウンドを活かし、高い位置までガンガン脚を突き上げて蹴る。彼は避けたり、受けたり、何も反撃をしてこない。
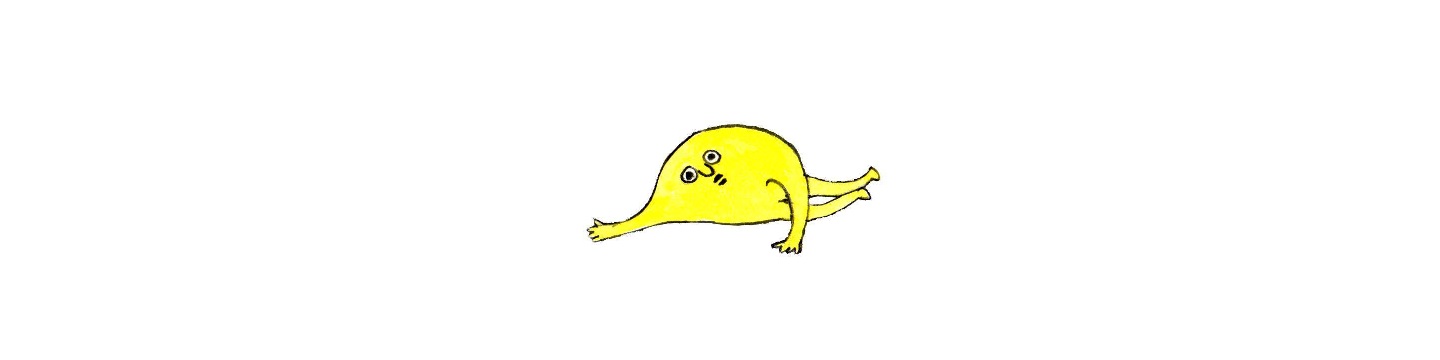
涙が頬を伝うのと同時に、ほんの少し征服感を憶えていた。きっとこの罪悪感によって、私は彼の「忘れられない存在」になれたに違いない、と思ったからだ。申し訳ないという気持ちから、愛してくれるかもしれない。
頬の傷に絆創膏を貼った姿が何とも不良っぽく見えたらしく、私はしばらくの間「番長」と呼ばれることになる。彼は先生に「女の子の顔に傷をつけた」と大層怒られ、後日、親と共に家まで謝りに来るはめになった。当然、私たちのロマンスがそこから発展することはなかった。
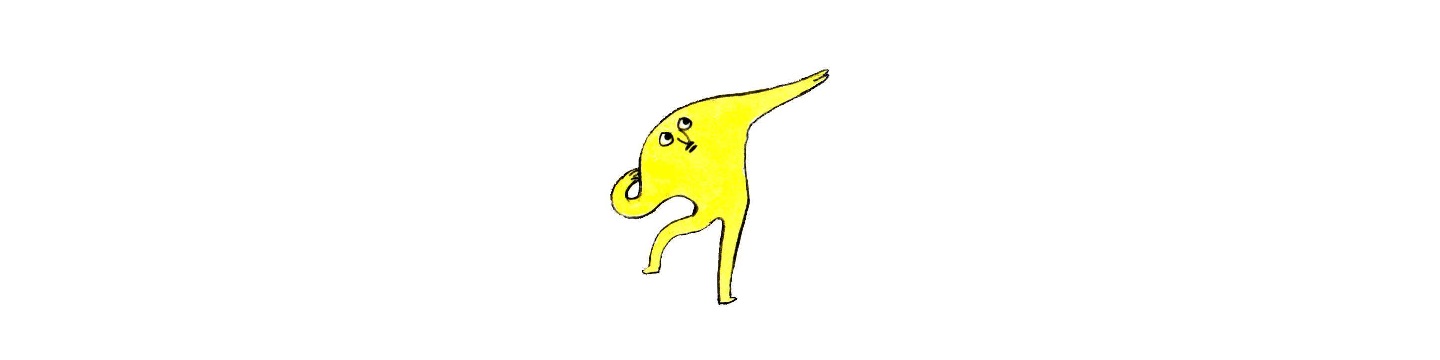
これはサブカルクソ野郎どもによくある「メジャー嫌い」嗜好にかなり似ている。ヒットチャート上位の曲は聴きたくない。ベストセラーはなんとなく読みたくない。平積みされている本より、棚の中から自分だけの感覚で選んだ本を読みたい。保証されていない、予想のできない愛を見つけたい。
結論、万人が愛するものを愛したくないのだ。みんなと一緒はイヤだ! なんていう子供くさい心理。自分が大衆の一人だってことは、もう何年も前に気付いているくせに、まだ自分だけの何かを見つけたいと思ってしまう。特別にはもうなれないかもしれない、でも特別を見つけられる人になりたいと思ってしまう。だって万人に愛されている人は、私の愛を必要としていない。私を必要としていない人を、私は愛せない。
ロマンスをはじめるための本
インドやカンボジアなど様々な国を旅する中で出会った人々の笑顔の写真を集めた写真集。知らない人の笑顔を見るだけで、遠い国の「誰か」がとても身近に感じられる。愛することも愛されることも全人類に備わった能力なような気がしてくる。
- 著者
- 三井昌志
- 出版日
- 2014-08-15
おじいちゃんと孫、同性の同級生、バツイチOLと大学生などの様々なデートを描いた短編集。人を好きになったり、心が動くことに年齢も性別も関係なく、様々な好きの形があると思わせられる一冊。読んでいる中で、自分が好きだった人がフラッシュバックし続ける……。
- 著者
- 瀬尾 まいこ
- 出版日
- 2014-05-20
この記事が含まれる特集
チョーヒカル
ボディペイントアーティスト「チョーヒカル」によるコラム。および本の紹介。体や物にリアルなペイントをする作品で注目され、日本国内だけでなく海外でも話題になったチョーヒカルの綴る文章をお楽しみください。
もっと見る 